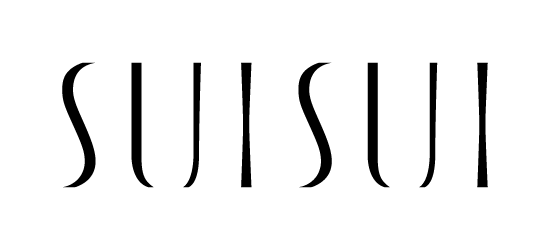2022/12/17 16:37
最近思っていること
水々を始めて4ヶ月くらい経った。Instagramをつくり、ONLINE SHOPを立ち上げて、骨董市に出店し。最近は、毎週土曜日に新作を販売することをルーティンにし始めた。
週末に買い付けに行って、帰ってきて洗って、平日の始業前や在宅ワークの休憩時間に撮影し、ONLINE SHOPにアップする。整理したり、仕組みにしたり、細かい作業は好きなほうで、ぽつぽつとつづけている。
買い付けはほんとうにたのしくて、とくに「これだ!」と思うものが見つかったとき、わたしの目はものすごく輝いているんじゃないかと思う。生きてるって感じがする。これだからやめらんないな、と毎度思う。そして売れると、自分の見てきたものが認められたようで、うれしくなる。水々で扱う品物の基準は、わたしのこころが動くこと。それだけはブレずにつづけたいと思っている。
でもわたしは本当に飽き性で、この短期間で、写真の雰囲気、Instagramの雰囲気がころころ変わっている。
統一感のあるアカウントに憧れて、最初は背景シートを使って撮ることに決めて、そしたら背景が統一されて撮るスピードも速かったけど、秋ごろには単調な背景と作業に飽きてしまった。
だから最近は、部屋の壁紙と机を質感のある白に変えて、それを背景にしたり、すこしスタイリングを加えるなどしている。そしたら撮り方にムラが出て、技量のなさにがっかりしてしまった。
写真って、どうしたらうまくなるの?
飽き性を自覚しながら、でもセンスのあるお店にしたいとも思っていて、もっと上手に写真を撮りたい、そもそもセンスってなんだ?という2つが、目下の課題となった。
自分で考えていてもわからないし、せっかくなら聞いてみようと、お世話になっているカメラマンさんに、どうしたら上手になるのか聞いてみることにした。
伊藤まさこさんのInstagramが好きなので、見てもらった。そしたら、「丸と四角」「余白の切り取り」「写真の配置のバランス」に個性があるねと教えてくれた。
友だちにも見てもらったり、そのあと自分で考えたりしていて、「ひとつはずす」「彩度やコントラストが低め」という共通点も見つかった。
カメラマンさんが言うには、そういう共通点を見つけて真似したり、同じ構図の写真を隣に並べたりしてみるといいよ、とのことだった。
そしてひるがえって、これまでわたしが撮ってきた商品写真のなかで気に入っている写真を眺めてみると、「2個並ぶ」「光」「つや」「ハの字に並べる」「集合体」が好きらしいということもわかった。
真似しつつ、やってみる。
写真の飽きの理由は、インプットの少なさだった。だから最近は伊藤まさこさんの本の写真を見る時間を増やして、撮るときに思い出せるようにし始めている。そしたら、「あ、かわいいな」と撮りながら思う瞬間も増えて、また撮ることがたのしくなってきた。
センスって、どうやったら身につくの?
「センスがいい」って、最強だなと思っている。美しくて、いやな気持ちにならないし、見ているこちらもしゃんとする。一貫した軸がある。誰かに教えても喜ばれて、自分までセンスがよいように思われる、だからどこか覚えておきたい存在。そんなお店、そんな人になりたい。
今度は、「センス」を会社のアイデンティティのひとつに掲げているアートディレクターさんに、どうしたらセンスを獲得できるか、聞いてみることにした。そしたら、
「真似とこだわり」
だと教えてくれた。いいと思うものを模写する、とにかく真似る。そして、いいと思った瞬間を切り取ることに、ミリ単位でこだわる。それをやり尽くして意識しなくなったころに、センスが獲得できているんじゃないか。
センスって、感覚。だれかの感覚が軸になっていて、そこからブレないこと。表現にもブレがないこと。「これでいいや」じゃなくて、「これがいい」が研ぎ澄まされたものが、「センスがいい」をつくっていく。
お二人に話をきいてみたら、似ていることを言っていた。つまり、わたしがやるべきことは「真似とこだわり」なんだと。ひとつの答えにたどり着いたこのごろ。
紙ものをつくる
最近はそんなことを考えながら水々をやっている。お店をやっているとお世話になっている方が買ってくれることもあって、そのきっかけで、水々の紙ものをつくろうというたのしいプロジェクトがはじまろうとしている。
ショップカードがないので、つくりたいなと(こないだの大江戸骨董市では、トレーシングペーパーをちいさく切って、InstagramのIDだけ書いて配った)、思いながら、まずはこれまでちょこちょこと集めてきた好きな紙ものを、とりあえず見てもらうことになった。同世代のデザイナーさんふたりも一緒に見てくれて、最終的によさそうなものがこれだけ残った。

見せながら、話しながら、キーワードになりそうな言葉が出てきた。
「パターン」「集合体」「手書き」「メモ」「小説」「途中」「手づくり感」「チラシ」「包装紙」「ペラペラパリパリ感」「余白多め」「青と緑のあいだの水色」「かわいさとエレガントさ」「イラスト」「線画」
なかでも、
「包装紙をつくる」
「一節の読み物(集めると連載になる)」
「素材をつくる」
という言葉がとくに印象に残った。いつも品物を包むときは、古い新聞紙を使っている。丈夫だし、使うことや捨てることにお互い罪悪感を持たなくて済む合理的な資源だから。そんな素材を、つくることができたなら?
…品物がかわいい包装紙にくるまれていて、開けてみたら内側には過去の商品の写真や水々のエッセイが載っている、思わずとっておきたくなる紙もの。クシャっとなってもそれはそれでかわいくて、知りたいと思える人にだけメッセージが伝わる。ほかに資源を必要としない、梱包とメッセージ、アーカイブの一体型…
めちゃくちゃいいじゃん!